いろんな本を読んで考えたことをまとめています。
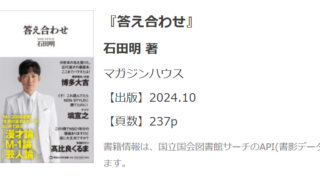 読書感想文
読書感想文 石田明『答え合わせ』で漫才の身体性について考える
M-1で優勝する難しさの正体M-1で優勝する難しさについて、石田明『答え合わせ』(マガジンハウス新書)を読んで、改めて整理できました。決勝に進むためには、観客席がお笑いマニアだらけの準決勝で求められる“通好み”要素に対応するのが必須だけれど...
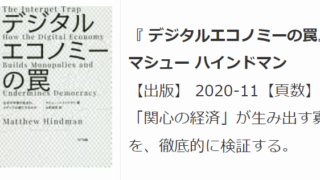 読書感想文
読書感想文 マシュー・ハインドマン『デジタルエコノミーの罠 なぜ不平等が生まれ、メディアは衰亡するのか』で“空想のインターネット”の夢から覚める
Web戦略を語ろうとする“オールドメディア”の人間は必読テレビ・ラジオ・新聞・雑誌といったいわゆる“オールドメディア”の人間がWeb戦略を語ろうとするなら、絶対に読んでおかなければいけない本でした。マシュー・ハインドマン『デジタルエコノミー...
 読書感想文
読書感想文 エドワード・スノーデン『スノーデン独白 消せない記録』でアメリカ政府の監視を実感した思い出
世界中の市民の通信を盗み見るシステムをNSA=アメリカ国家安全保障局が運用していると2013年に内部告発したエドワード・スノーデンの自伝『スノーデン独白 消せない記録』(河出書房新社)。スノーデンは告発からずっとアメリカ当局に追われていて、...
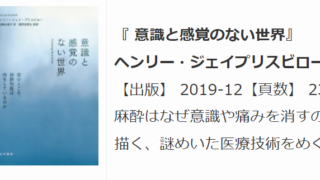 読書感想文
読書感想文 ヘンリー・ジェイ・プリスビロー『意識と感覚のない世界~実のところ、麻酔科医は何をしているのか』
「先生!しつこいです!その患者さんは間違いなく絶食しています!」と担当看護師から言われた麻酔科医は、その4歳の患者本人からの申告、「僕、シリアルバー食べちゃったよ😏」とどう向き合えば良いのか…。アメリカの麻酔科医ヘンリー・ジェイ・プリスビロ...
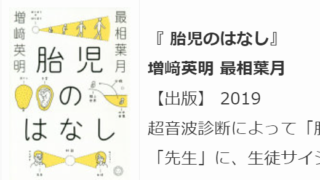 読書感想文
読書感想文 増﨑英明 最相葉月『胎児のはなし』で夫のDNAが胎児経由で妻の体内を漂っていることを知る
父親のDNAが胎児を通して母親の体内に入り込み、何らかの作用を母親の肉体に及ぼしていることが最近分かってきたそうです。それって夫ウイルスが妻を蝕んでいるってことでは!?この話を出産経験のある女性にすると、怪談を聞いてしまったように恐怖に震え...
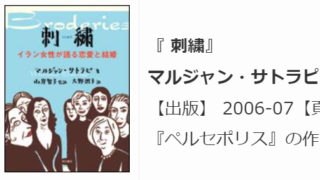 読書感想文
読書感想文 マルジャン・サトラピ『刺繍―イラン女性が語る恋愛と結婚』でイスラム女性の恋愛事情を知る
漫画のタイトルに使われた隠語"刺繍"の意味に度肝を抜かれました。どういう意味か分かりますか?言われてみれば納得の意味で、イスラム社会を理解するのに役立つ隠語だと思います。ちなみに"全面刺繍"もあります。イスラム主義勢力タリバンがアフガニスタ...
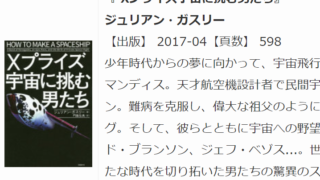 読書感想文
読書感想文 ジュリアン・ガスリー『Xプライズ 宇宙に挑む男たち』でアメリカ人を宇宙開発に駆り立てる原動力を理解する
アメリカでは、イーロン・マスク率いる民間宇宙開発会社スペースX社が民間人だけの宇宙旅行を成功させています。スゲー!と思う一方で、何がそこまで、アメリカ人を宇宙開発に駆り立てるのだろうと、いまいちピンとこないという人もいっぱいいると思います。...
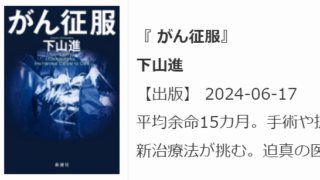 読書感想文
読書感想文 下山進『がん征服』が専門家にガチで仕掛ける“まともな論戦”
“論戦”をむやみに見かけるようになったSNS時代ですが、だからこそ逆に“まともな論戦”はめったに見かけなくなってしまったSNS時代。そんな時代に、“まともな論戦”をガチで仕掛ける姿に震えるな、この人はペンの力を信じているのだなと、姿勢を正し...
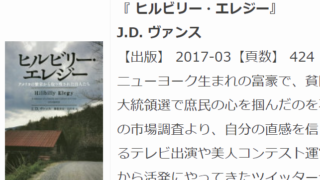 読書感想文
読書感想文 J.D.ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』でトランプ2期目に備える
ドナルド・トランプのアメリカ大統領復帰という可能性に向けて読んでおくべき本が、J.D.ヴァンス『ヒルビリー・エレジー アメリカの反映から取り残された白人たち』です。トランプ大統領が誕生した2016年にアメリカで出版され、トランプ大統領誕生の...
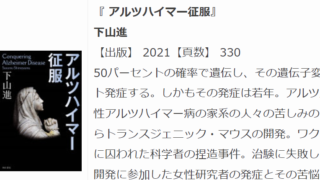 読書感想文
読書感想文 下山進『アルツハイマー征服』で学ぶ新薬開発の大変さ
アルツハイマー病治療薬の開発とアメリカFDAでの承認に向けての道のりを描いた下山進 『アルツハイマー征服』が上梓されたのが2021年1月で、FDAで承認されるかどうか関係者が息をのんで待っているというタイミングでした。発売後すぐに読んでいたので、本に登場する青森の家族性アルツハイマーの一族にすっかり感情移入してしまって、FDAの判断をドキドキしながら待っていました。