万能なインタビューのテンプレ
アナウンサー用語に、「きっかけ、ご苦労、今後の抱負」というものがあります。インタビューのテンプレートで、このテンプレに沿って聞けば、とりあえずインタビューが成立するというものです。
「こうした取り組みを始めたきっかけは?」
「ご苦労もあったんじゃないですか?」
「今後の抱負を聞かせてください。」
どちらかと言うと、このテンプレでしか聞けない稚拙さを戒める時に使われがちです。しかし、短い時間で、視聴者に納得感を与えるインタビューとなると、結局はこのテンプレの万能さに頼ることが多いのも現実です。
渡邉雅子『論理的思考とは何か』ですっきり整理!
テレビやラジオで、正確には“日本の”テレビやラジオで、このテンプレが威力を発揮する理由が、渡邉雅子『論理的思考とは何か』(岩波新書)を読んで分かりました。
2025年ベスト読書体験が早くも決まりました。これを読めば、大学受験どころか、大学のレポート、就職活動、さらには社会人にもついてまわる“作文”で求められているものの正体が分かります。あの“作文”に何を求めているかって、評価する側にまわって驚いたのですが、実はほとんどの人がまともに言語化できていないんですよね。さらには、日本の国語教育に多い「この時の登場人物の心情として正しいものはどれか?」といった設問は、何かと批判されがちですが、批判も回答もいまいちずれている気がしていました。そのあたり、全部まとめて、めちゃくちゃすっきり整理してくれる本だったのです。図書館で借りて読んだのですが、これは何が何でもわが子にも読ませなきゃと、読破した瞬間に注文しました。2025年ベスト千円札の使い道に決定です。
世界共通で不変のものだという思い込み
『論理的思考とは何か』という問いに対する、この本の回答を一言にすれば、
「場合による」です。
拍子抜けするかもしれませんが、世界共通で不変なものだと思い込んでいた自分に気付かされ、いろんな種類の論理的思考があることに気付かされることの価値は絶大です。私も、思い込んでいました。私の場合は、東大の教養学部時代に野矢茂樹『論理学』を受講した時の衝撃の大きさから、“形式論理”の射程圏を過大評価していた気がします。
なんか、めっちゃすごいこと習った気になるんですよね。実際、めっちゃすごいことなんですが、実社会のほとんどの命題は“真”or“偽”に二分することなんてできないわけです。となると、実社会におけるほとんどの論理って、その社会の価値観を反映した文化的側面から逃れられないわけです。これを、厳密な“形式論理”とは違う“本質論理”と呼ぶことが、本の冒頭で宣言されます。
“論理の型”は国によって異なる
筆者の渡邉雅子さんが、こうした研究を始めたきっかけは、アメリカの大学に留学してエッセイと呼ばれる作文を提出した時に、「評定不可能」と突き返され続けたことでした。しかし、アメリカ式エッセイの型に合わせて書いて提出した途端に、評価が一気に急上昇したのだそうです。それぞれの文化に、それぞれの“論理の型”があり、それに沿っているかどうかで、論理的かどうかを判定している部分が極めて大きいのです。
これは、まったく違う“論理の型”に触れることで、とてもよく分かります。例えば、フランス。ギリシャ文明から続くヨーロッパの伝統を引き継ぐフランスにおける“論理の型”は、弁証法なんだそうです。一般的に正しいと思われている“正”があって、それを否定する“反”があって、そこに生じた矛盾を本質的に統合することで“合”に至るという、あれです。ヘーゲルのアウフヘーベンです。フランス式小論文“ディセルタシオン”は、この形式で書くことがマストで、大学入学資格を得る試験であるところのバカロレアなどでも出題されるのだそうです。つまり、フランスの高校生は、弁証法形式の作文を書く訓練を徹底的に繰り返すということなのです。しかも、結論的な“合”のパートにも、それでもやはり矛盾の芽が潜んでいること、次なる弁証法をにおわせるのがお決まりとのこと。フランス革命に完成はなく、永遠に続いているのです!めっちゃ異文化!
この話題をある人にしたところ、
「そういえば、前の職場にフランス出身の同僚がいて、何かと揚げ足を取る人と評価されがちでした。」と語っていました。ディセルタシオンでは、命題の中の用語の定義などから自分で矛盾をほじくり出して語ることが求められます。そうしたフランス式“論理の型”が、日本の職場でなじみにくい場面もあったのかもしれません。
また、ディセルタシオンにおける論拠は、古典の厳密な引用じゃなきゃだめなんだそうです。ホッブズやスピノザなどを引用するのです。古典の引用を上手にできることが論理的だという価値観は、古くて新しいなと感じました。というのも、ちょうど同じ時期に松本いっか『日本三國』という漫画を読んでいて、その主人公の軍師キャラが論理的であることの表現として、中国の古典を引用しまくる描写がお決まりだからです。読んでいて、これはこれで価値観として成立するものだなと感じていたところでした。フランスで、『日本三國』めっちゃウケそう。
“論理の型”は領域によっても異なる
このフランス式小論文ですが、その採点コストの高さがとんでもないことは、容易に想像できます。実際、フランスでも、しょっちゅう議論になるそうです。しかし、ディセルタシオン教育こそが、主権者としてのフランス国民に求められる“政治的主体としての市民”を育成するための手法だとして、そのコストを社会が許容し続けているとのこと。
実は、この“政治的主体”というのが鍵で、こうした“論理の型”は、国だけではなく分野によっても異なるというのが筆者の主張です。そして、フランスに代表されるような“論理の型”は、“政治”領域における“論理の型”でもあるのです。
合理性に関する二つの指標、形式・実質、客観的・主観的をかけ合わせると、4つの領域に分けることができ、それぞれの領域を4つの分野と国に対応させて論じていくのが、この本の大きな仕掛けです。すなわち。
| 形式合理性 | ||||
| 経済領域 アメリカ | ↑ | 法技術領域 イラン | ||
| 主観的 | ← | → | 客観的 | |
| 社会領域 日本 | ↓ | 政治領域 フランス | ||
| 実質合理性 |
客観的な合理性を重んじる中で、
形式合理性を重んじるのが“法技術領域”であり、イラン。
実質合理性を重んじるのが“政治領域”であり、フランス。
主観的な合理性を重んじる中で、
形式合理性を重んじるのが“経済領域”であり、アメリカ。
実質合理性を重んじるのが“社会領域”であり、日本。
といった分類です。たしかに、フランス式小論文が目指すところは、いろんな人がいる社会の主権者として、客観的にいろんな人の立場に目配りして議論することです。そして、あらゆる命題に矛盾が含まれていると疑う姿勢なわけで、白黒つける形式合理性ではなく、実質合理性の性格が強くなるのが当然です。それは確かに、政治領域における議論の合理性のあり方でもあります。ここに、聖典や憲法といった常に“真”とされうる、形式合理性と相性の良い概念が入ってくると、それは“法技術領域”でありイラン的な合理性のあり方と類型化されるわけです。イランにおける合理性の話も、猛烈に興味深いので、ぜひ本で読んでみてほしいところ。
アメリカ的・経済領域な“論理の型”の圧倒的コスパ
そして、筆者は、アメリカ的な“論理の型”こそが唯一絶対の合理性だという風潮に、強い危機感を示しています。アメリカの“論理の型”は、最初に主張をどんと述べ、その根拠となる事実を強い順に3つ並べ、最後に主張を再び述べる直線的なものです。圧倒的に効率が良くて便利なのは間違いありません。と言うのも、実はこの形式のエッセイがアメリカに定着したのは、アメリカで高等教育の需要が爆発的に高まった1970年代で、大量の論文を素早く採点しなければいけないというニーズもあったからなのです。それまでの、フランス的要素もあったであろうヨーロッパ的“論理の型”との決別によって獲得した、圧倒的コスパなわけです。そりゃあ、ビジネス書は、このスタイルこそが唯一絶対の合理性だともてはやすに決まっています。もしかしたら、アメリカ自身も、割り切りの結果として採用したに過ぎない“経済領域”の“論理の型”を内面化しすぎて、あらゆる領域に援用してしまう病から逃れられなくなっているのかもしれません。私自身が教育システムに最適化するのが超得意だったから分かるのですが、高い評価を得るためには、採点基準となる“論理の型”を徹底的に内面化することが一番の近道です。これをアンラーニングするのは、なかなか大変だと思います。
“お気持ち”を大切にする日本的・社会領域な“論理の型”
最後に、“社会領域”に対応した日本の合理性について。社会が統制と秩序を保つためには、明文化されないそれぞれの“お気持ち”に配慮しあいながら、状況に応じてそれぞれが適切な態度や行動を選択することこそが合理的なわけです。そんな日本人を育成するために学校で指導される“感想文”は、
序論として書く対象の背景を、
本論として書き手の体験を、
結論として体験から得られた書き手の成長と今後の心構えを
書くというスタイルになるわけです。そして、教室では、友人が書いた作文の感想を求められ、友人の“お気持ち”に触れたことで自分の“お気持ち”にも変化が生まれました的なことを発表してみたり。
“お気持ち”と揶揄した書き方を勝手にしているのは私で、本の筆者はこれっぽっちもそんな書き方はしていません。私がこういう書き方をしてしまうように、客観的な合理性とはかけ離れた“自分の気持ち”を論拠にした言説を、“論理の型”から外れているとバカにして、“お気持ち”と揶揄する風潮が強くなっています。私自身の中にも、その感覚があります。しかし、そこには実は優劣が無くて、適切な領域で適切な“論理の型”を使い分けることこそが大切なのです。
そうやって考えてみると、「きっかけ、ご苦労、今後の抱負」は、まさに日本のテレビやラジオと相性が良いのは納得だなと思った次第です。テレビやラジオが主に担っているのは、“社会領域”であり、何よりここは日本です。
「こうした取り組みを始めたきっかけは?」=序論 対象の背景
「ご苦労もあったんじゃないですか?」=本論 体験
「今後の抱負を聞かせてください。」=結論 今後の心構え
と、“感想文”の構成と見事に一致しています。見ている方も、無意識に慣れ親しんだ“感想文”と一致しているから受け止めやすいことでしょう。何より、答える方も、何かのイベントごとに書かされる“感想文”と一致しているので、自然に答えられそう。なるほど、よくできたテンプレートです。
ただし、“社会領域”の“論理の型”もまた、いたずらに他の分野に当てはめようとするとろくなことにならないことを心しておいた方が良さそうです。SNSもまた、“社会領域”の“論理の型”が基本だと認識しています。SNSにおいて“真”であると太鼓判を押された命題があっても、主観的合理性な領域における判定であって、客観的合理性が求められる“政治領域”や“法技術領域”で通用するかは別の話なのです。
「はい論破」と雑な論戦があふれている今の時代、猛烈に参考になる本でした。
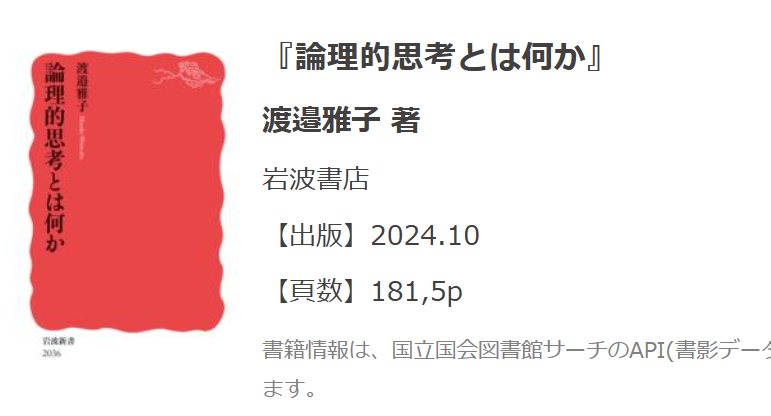

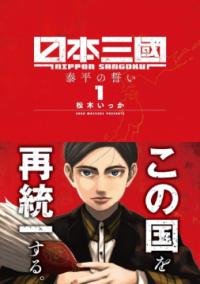

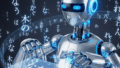
コメント